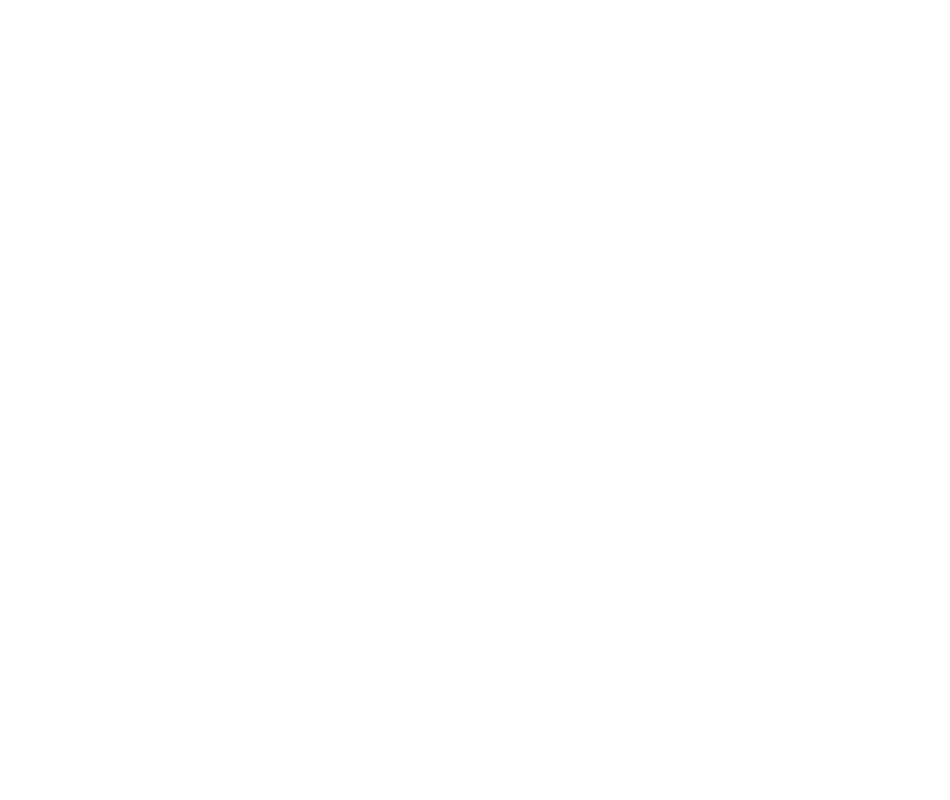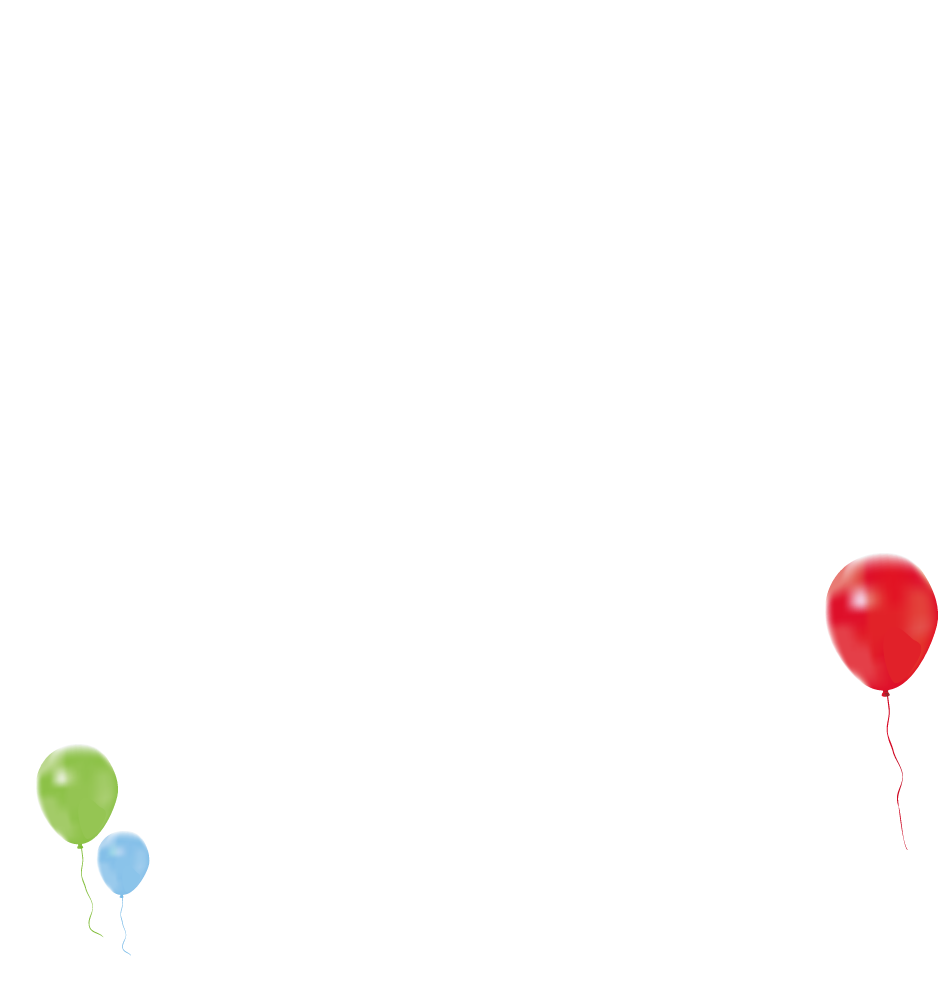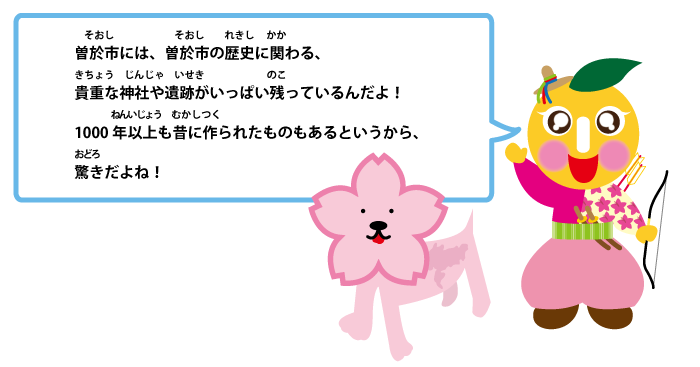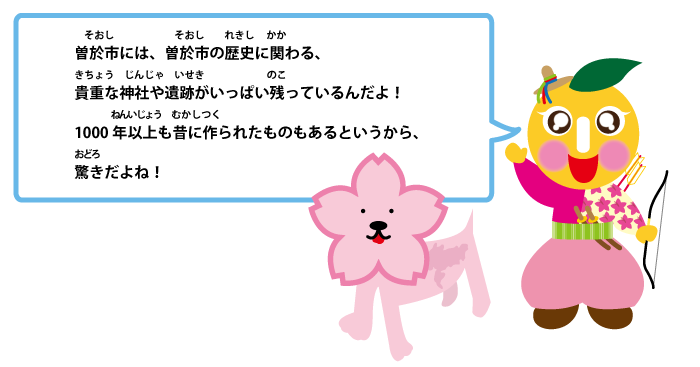
住吉神社(末吉)
流鏑馬が行われる住吉神社は、参道から長い階段を上がると神社や杉の大木があります。
住吉神社は、郷社でしたが、昭和7年に県社へ昇格。祭神は、底筒男命、中筒男命、表筒男命。
岩屋観音(大隅)
岩屋観音は、岩壁に江戸時代元禄期の行仙による刻字等があり、文明18年(1486年)に開山したといわれています。
岩屋観音に並ぶように吉田大明一圓(明治時代中頃)の刻んだ長谷寺式十一面観音石仏の本尊や善光
寺式三尊などが自然石に美しく彫刻されています。
恒吉太鼓橋(大隅)
岩川・市成街道の長江川に寛政2年(1790年)3月にかけられた石橋です。
県内最古級のアーチ式石橋で、長さ15.5メートル 幅2.8メートルです。
岩川八幡神社(大隅)
八幡神社は万寿2年(1025年)京都の石清水八幡宮より勧請。大正3年現在地に移転。
昭和13年には社殿を新築し、祭神は、応神天皇をはじめ武内宿弥、神功皇后、玉依姫命、仲哀天皇、天照大神、伊邪那岐命、保食神。
投谷八幡宮(大隅)
投谷八幡宮は、大谷の宮ヶ原に鎮座し、大隅正八幡(鹿児島神宮)の別宮で、祭神は、神功皇后、応神天皇、仁徳天皇。和銅元年(708年)創建と言い伝えられ、敷地内には大きなイチョウの木がそびえています。
島津氏の時代も手厚く遇されており、平成15年鹿児島県有形文化財に指定されました。
日光神社(財部)
奈良時代の和銅3年(710年)に鴨頼長によって創建されたと言い伝えられています。財部という地名に密接なかかわりのある神社でもあります。
熊野神社(末吉)
鬼追いの行われる熊野神社には、境内に五輪塔があります。鬼が暴れまわる参道には、もと光明寺の仁王像が2体鎮座し、この仁王像は本尊を守る役割があります。
溝ノ口洞穴(財部)
霧島山系の湧き水が浸食し、数千年の長い年月をかけてつくられたとされる洞穴は、横13.8m.高さ8.6メートル、全長は昭和41年に関西大学探検隊の調査で224メートルまで確認されています。
洞穴からは、今でもこんこんと地下水が流れ出し、地元の人の話では、洞穴に犬をいれたら高千穂の峰に出てきたという伝説も残っています。昭和30年鹿児島県天然記念物に指定されました。
澤田神社(財部)
戦国時代に建てられた澤田神社には、7つの能面があり、その内の1つは、島津忠国が奉納した約550年前の能面で、澤田神社よりもさらに古い歴史を持っています。